2024年07月04日
アウトリーチ実施のご報告

専門家を派遣し、出前授業を実施する恒例の「アウトリーチ事業」が7月3日、地元の市立和歌浦小学校で開かれました。当館が地域貢献の一環として取り組んでおり、当館でクレパス画の講座を持つ洋画家の土井久幸さんが講師として教壇に立ちました。
2年生24人と5年生23人が受講し、2年生のテーマは「シュールな絵を描こう!」。山より大きな砂時計やブランコに載っているパイナップルといった「んなアホな」と思わせる絵です。土井さんは「風景と物を組み合わせると、描きやすい。何描いてもええよ」と声掛け。2年生は図鑑を見ながら、「森に棲むサメ」「家より大きなアルマジロ」「雲より高い竹」など自由な発想で鉛筆を走らせました。

一方、5年生のテーマは「イメージを描く」。例えば、炭酸飲料の缶をモチーフに選ぶと、ふき出る泡も一緒に描くという内容で、連想し感じたことを表現します。土井さんは「まずはモチーフを決めて、はみ出るぐらい大きく描いて。次に背景を決めて」とアドバイス。ランプ、空き瓶、リンゴなど土井さんが持参した物を参考にしたり、想像を膨らませたりして画用紙に向かっていました。

両学年の児童ともクレパスで色を塗った後、絵の具で仕上げます。「白い所を残さず、いろいろな色を使ってみよう」といった指導を受けながら、真剣に取り組んでいました。授業後、土井さんは「面白い絵がたくさん出来上がりました。いい感じに描けていましたよ」と評価していました。

児童の作品は11月に当館で開かれる「みんなの文化祭」で展示される予定です。
※クレパスは「サクラクレパス」の登録商標です







児童の作品は11月に当館で開かれる「みんなの文化祭」で展示される予定です。
※クレパスは「サクラクレパス」の登録商標です




2024年06月02日
クレパス画教室開催のご報告

洋画家の土井久幸さんを講師に迎えた人気講座「クレパス画教室~クラシカルな表現を楽しむ~」が5月22日に当館で開かれました。土井さんが訪れたフランス・アルザス地方の街角を題材とし、受講生はアドバイスに耳を傾けながら、欧州らしい陰影感に満ちた風景を描いていました。
土井さんは地元で絵画教室を主宰し、和歌山ゆかりの芸術家に贈られる大桑文化奨励賞(大桑教育文化振興財団主催)を受賞。全国各地で個展を開催しています。クレパスの色合いを生かした個性的な「情景画」が高く評価されています。
受講生はまず、「転写」という技法で、キャンバスに建物や噴水、道路などの輪郭を写し取っていきます。木炭で濃淡をつけて塗り込んだ後、クレパスで色を付けていきます。
テーマとなっているクラシカルな表現について、土井さんは「影の色は黒が基本ですが、黒では画面が濁るため、茶色と青色を混ぜて重ねてください」「全体を茶色でぼかしていくとクラシカルな風合いになります」と説明。制作途中の受講生の作品を見て、「空気感が良く出ていますよ」などと講評していました。
ペインティングナイフで削ると、最初に塗った下地の白色が浮き出て光が当たった部分に見えるなど受講生はクレパス画の技法を学びながら、緻密な作業に取り組み、最後に定着スプレーを振りかけて完成。受講者は約5時間をかけた力作に満足そうな表情で、「本格的に教えてもらって本当に楽しかった」「初めての体験でしたが、説明も良く分かったし楽しく制作できました」と感想を寄せていました。土井さんは「みなさん良い感じの作品に仕上がりました。絵画は描き忘れがあっても個性。失敗を恐れずどんどん描き進めてほしい」と話していました。
※クレパスは「(株)サクラクレパス」の登録商標です



※クレパスは「(株)サクラクレパス」の登録商標です


2024年05月25日
TSUYOSHI ALL SESSIONS LIVE 2024開催のご報告

当館恒例の音楽イベント「TSUYOSHI ALL SESSIONS LIVE 2024 in CUBE・A」が5月19日に開かれました。地元で活動する砂山剛さん(写真中央)率いるアマチュアロックバンドが熱演を繰り広げ、計18曲を歌い上げました。「最高のロックン・ロール・ショー」を届けたいとの言葉通りの弾けたステージ。雨にもかかわらず訪れたファンら約150人が酔いしれました。
砂山さんは、秋にも和歌山市内のライブハウスで演奏活動をしており、当館でのライブは既に十数回に達しています。今回はギター、ベース、ドラム、キーボード、コーラスの9人編成で、洋楽・邦楽のロックを中心とした楽曲を披露。確かなテクニックに裏打ちされたビートが心地よく響き、汗だくになったメンバーの熱気も伝わり、バンドを貫くロックスピリットが会場を包みました。
最後に砂山さんがそろいのTシャツを着たメンバー全員を紹介した後、「来年5月もアート・キューブでライブをやります。また来てもらえたら」と呼びかけ、大きな拍手を浴びていました。



2024年05月16日
音楽祭2024ご報告ブログ

演奏会でつながる人と地域を目指し

「和歌の浦アート・キューブ音楽祭2024」が5月5、6両日に当館で開かれ、地元で活動するアンサンブル団体や吹奏楽グループ計11団体が出演しました。出演者は総勢約200人、2日間で計4時間半に渡って約60曲が演奏される大規模なイベントとなりました。会場は立ち見が出るほどの盛況ぶりで、計約400人の観覧者が多彩なジャンルの音色を満喫していました。
「“音楽でつながる”コミュニケーションづくりの音楽祭」を目的に今回が3回目の開催です。初めて設けられた5日夕の前夜祭には、今年結成20周年を迎えたラテンビッグバンドの「ORQUESTA DE TASKERUO」(オルケスタ・デ・タスケルオ)が登場しました。スタンダートジャズやポップス、マンボなどのナンバー計10曲をパワフルに熱演。音楽祭の幕開けを飾るにふさわしい心地良いライブとなりました。


6日にステージに立ったのは、前半がトロンボーン5重奏の「和歌トロ技術研究所」▽木管3重奏の「アンサンブル リエタメンテ」▽サックス4重奏の主婦4人組「SaxQuartet COLON」▽女性によるクラリネット4重奏の「シャ・ノワール」▽5人組の金管アンサンブル「W.A.cube ブラス」といったアンサンブル団体。後半の出番は吹奏楽団で、はつらつとしたサウンドを披露する海南市立第三中学校吹奏楽部▽同吹奏楽部卒業生が中心メンバーの「Spielen Wind Orchestra」(シュピ―レン ウインド オーケストラ)▽「わかやまと奏でる」をモットーに活動する和歌山大学吹奏楽団▽Brethren DUB Sounds(ブレスレン ダブ サウンズ)&和歌山市立明和中学校吹奏楽部です。


童謡やクラシック、映画音楽、ポップスなどをしっとりとした曲調を奏でたり、テンポの良いリズムで魅了したり。各グループの楽器が気持ちよく響き合い、会場を包み込みます。自然と手拍子も巻き起こり、雰囲気は最高潮に。最後に吹奏楽の各グループによる合同演奏があり、「蛍の光」で締めくくりました。観覧者からは「懐かしい音楽があり、楽しく聴かせていただいた」「昨年より楽しみにしていました。感動ありがとう」と満足そうな声が届きました。来年の音楽祭は5月5、6両日で計画しています。







(上から順にORQUESTA DE TASKERUO、和歌トロ技術研究所、アンサンブル リエタメンテ、SaxQuartet COLON、シャ・ノワール、W.A.cubeブラス、海南市立第三中学校吹奏楽部、和歌山大学吹奏楽団、Spielen Wind Orchestra、Brethren DUB Sounds&明和中学校吹奏楽部)

タグ :和歌の浦アート・キューブ音楽祭和歌トロ技術研究所アンサンブル リエタメンタオルケスタ・デ・タスケルオSaxQuartet COLONシャ・ノワールW.A.cube ブラス和歌山大学吹奏楽団Spielen Wind OrchestraBrethren DUB Sounds
2024年04月29日
ブラスフェスタ開催のご報告

和歌山のアマチュア金管楽器奏者の祭典「第17回BRASS FESTA」が3月31日、当館Aホールで開かれました。金管アンサンブル6団体がそれぞれの団体のカラーに染めた音色を高らかに鳴り響かせました。会場には満席となる約200人の観覧者が訪れ、金管楽器が織りなす迫力ある演奏を堪能していました。


ステージに立ったのは、当館の音楽祭をきっかけに結成された「W.A.cube ブラス」▽BRASS FESTA参加のためだけに集まる「ZUNDOCO BRASS」▽「和歌山大学吹奏楽団」の10人による金管チーム▽トローンボーンのみで編成する「和歌トロ技術研究所」▽日本情緒に満ちた曲に挑戦した「Brethren DUB Sounds(ブレスレン・ダブ・サウンズ)」▽20歳代の若手演奏家をメンバーとする「Felice Ensemble」(フェリーチェ・アンサンブル) 。映画音楽やアニメ音楽、ジャズの名曲、コンクールの課題曲などさまざまなジャンルの計17曲を披露しました。明和、海南第三、岩出第二の各中学校の吹奏楽部メンバーも加わって、総勢約50人で高校野球の応援曲としてもお馴染みの「アフリカンシンフォニー」などを合奏。祭典にふさわしく賑やかで心浮き立つ曲が続き、観覧者から大きな拍手が起きていました。


最後に今回を区切りに「BRASS FESTA」の休止が発表されました。観覧者からは「素敵なアンサンブルを聴けて、またの開催を楽しみにしています」「とても迫力があり、感動しました。是非とも続けてほしい」などの声が寄せられました。


写真は上からW.A.cube ブラス▽ZUNDOCO BRASS▽和歌山大学吹奏楽団▽和歌トロ技術研究所▽Brethren DUB Sounds▽Felice Ensemble

2024年04月03日
シェイプボクシング教室開催ご報告

>

「脂肪燃焼!!」「ストレス発散!!」と銘打ったシェイプボクシング教室が2月22日、29日、3月14日、3月28日に開かれました。多彩なキックやパンチの動作を取り入れたエクササイズで、30歳代から70歳代の受講生が心地よい汗を流しました。


講師は健康運動指導士の川村護さん。この道35年のベテランで、以前から当館でも体操教室を受け持っています。今回は体を動かす機会が少ない冬場に、汗をかいてもらおうと企画。参加者の募集開始直後に定員に達した人気講座です。二の腕や肩甲骨、ウエスト周辺など気になる箇所を効果的に動かすプログラムで構成され、歩数に換算すると、1回の教室で約1万歩となります。



3分間のエア縄跳びなどで体をほぐした後、軽快な音楽に合わせ、受講生はジャブやストレート、フック、アッパーといったパンチ、肘打ちやキックなどをテンポよく連続で繰り出します。川村さんから「しっかりウエストを回して」「肩や腰の動きは大きく」などのアドバイスが飛びます。パンチやキックは高くすれば、より筋力が鍛えられるといい、「相手が身長180㌢だと思って、向かってください」と声掛けをしていました。左右にステップを踏みながら、腰の入った姿勢で拳を突き出したり、美しい型のキックを見せたり。受講生は楽しみながら体を動かしていました。

開催回数を重ねるほど、より密度の高いプログラムになっており、終了後のアンケートで、「久しぶりに仕事以外で良い汗をかきました。色々な年代の人たちと知り合えてよかった」「すごく楽しかった。丁寧に指導していただき嬉しかったです」などの感想が寄せられていました。






開催回数を重ねるほど、より密度の高いプログラムになっており、終了後のアンケートで、「久しぶりに仕事以外で良い汗をかきました。色々な年代の人たちと知り合えてよかった」「すごく楽しかった。丁寧に指導していただき嬉しかったです」などの感想が寄せられていました。



2024年03月29日
苔テラリウムづくり教室開催ご報告



教室では、必要な材料が用意され、まずは土の入ったガラスポットに、多様な形をした石を選んで置きます。講師は「石ばっかりにして、石テラリウムにしないように」と声掛け。ハケで土に傾斜を付けたり、大小の石の配置により遠近感を出すなど工夫を凝らします。水をかけて全体を固定した後、川や道に見立てて青や白色の化粧砂を散りばめます。「手前で幅を広げ、末広がりにした方が見栄えが良いですよ」「砂をかくと、下の土が出るからダメですよ」などさまざまなアドバイスに、受講生は耳を傾けながら作業を進めます。

最後に主役の苔の登場です。カサゴケやタマゴケなど形状や毛並み、色合いの異なる8種類から好みに合わせて選択し、苔の組み合わせで立体感を醸し出します。受講生は全体のバランスを考慮しながら、形を整えた苔をピンセットで慎重に移します。「苔を使い過ぎてジャングルみたいになった」と笑い声も起きていました。

受講生は作品の出来栄えに満足そうで、「初めての体験でしたが、先生に分かりやすく教えていただき、なんとか完成させました」「すごく楽しく、かわいい作品が出来てうれしかった。大切に育てます」と喜んでいました。
受講生が制作した「苔テラリウム」

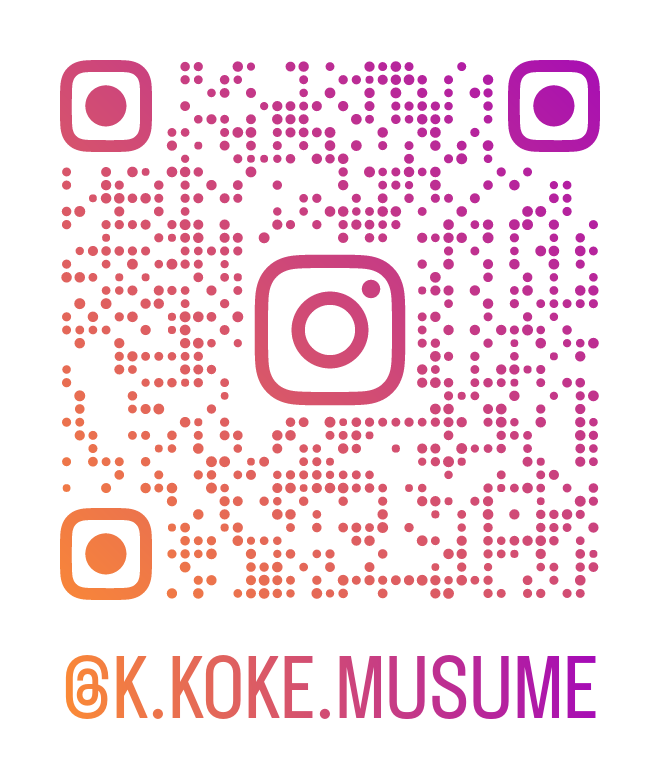
2024年01月12日
コンディショニング教室 開催ご報告ブログ
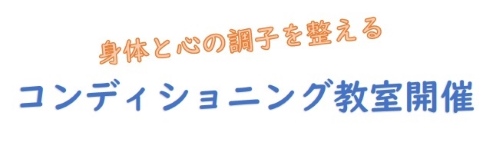

「身体と心の調子を整える」コンディショニング教室が昨年12月に開かれました。講師は昨年に続いてコンディショニング・トレーナーの橋本葉子さん。計4回に渡ってあり、受講生は入門編として紹介されたさまざまなエクスサイズを体感しました。
初日、橋本さんはトレーニングのアプローチとして「ほぐして×整えて×鍛える」ことの大切さを指摘。乱れた自律神経を整える「全身をさする体操」や「耳回りマッサージ」を紹介しました。次に血圧を安定化させる呼吸体操を披露し、「呼吸とともに体に緊張と弛緩をもたらすことで、自律神経の安定につながります」と声掛けをしていました。
2日目は呼吸法です。「10秒呼吸」とヨガの「交互の片鼻呼吸法」を行いました。「10秒呼吸」で呼吸に集中し、脳を休め心も体もリラックス。「交互の片鼻呼吸法」では、右手でナシカムドラー(人差し指と中指をしっかり曲げる)、左手はチンムドラーの形をつくります。上手く結べなかった受講生も指導に従い肩や肘、手首を緩めると出来るように。
2日目は呼吸法です。「10秒呼吸」とヨガの「交互の片鼻呼吸法」を行いました。「10秒呼吸」で呼吸に集中し、脳を休め心も体もリラックス。「交互の片鼻呼吸法」では、右手でナシカムドラー(人差し指と中指をしっかり曲げる)、左手はチンムドラーの形をつくります。上手く結べなかった受講生も指導に従い肩や肘、手首を緩めると出来るように。
3日目、養生功やヨガを用いて、立位での姿勢を整える方法の説明がありました。養生功は、伸びやかに気持ちよく行う健康体操(血液の循環を促進する) です。また、ヨガの一つのアーサナを分解したエクスサイズでは、立位姿勢での足の置き方や重心の取り方、体の軸の取り方で、脚や膝を守ることの大切さを学びました。
最終日は、寝た姿勢をとり、呼吸法を使った体幹の鍛え方に励みました。また、新聞紙を使って感覚を鍛える方法も披露。姿勢にも体を動かすにも、ほぐして整えることが大事で、今回の教室でもリセット法やほぐし方のエクササイズの紹介がありました。受講生は「体と心について重要な知識を分かりやすく教えていただき、よかった」「とても良いメソッドだと思いました。心身ともリラックスするよう心がけます」と満足そうでした。



最終日は、寝た姿勢をとり、呼吸法を使った体幹の鍛え方に励みました。また、新聞紙を使って感覚を鍛える方法も披露。姿勢にも体を動かすにも、ほぐして整えることが大事で、今回の教室でもリセット法やほぐし方のエクササイズの紹介がありました。受講生は「体と心について重要な知識を分かりやすく教えていただき、よかった」「とても良いメソッドだと思いました。心身ともリラックスするよう心がけます」と満足そうでした。



2023年12月16日
大人の粘土教室 開催のご報告ブログ

来年の干支の置物を作ろうと、年末の人気講座「大人の粘土教室」が12月2、9両日に開かれました。講師は当館スタッフの井上隆好さんで、募集開始直後に定員が埋まりました。今年は10人の受講生が辰作りを楽しみました。

針金にアルミホイルを巻いた骨組みや角、目玉などの部品は事前に用意。まずは、骨組みに粘土を張り付けて、形を作っていきます。 井上さんは「最初は細目にして、後で肉付けを」「足は鳥のように三本爪に」など細かくアドバイス。受講生は井上さんが手がけた完成品を手本に、粘土を扱っていきます。「動きがあって、強そうに見えるわ」「私、センスないわ」など軽口を交わしながら、納得できるまで形を整えていきます。

この後、角やひげを差し込んだり、鼻の造形をしたりと顔全体を仕上げていきます。次に背びれ作りです。背中の部分をつまみ道具で切り込みを入れます。受講生は手を水に濡らし、粘土を伸ばして質感を出すなど工夫を凝らしていました。

じっくり乾燥させた後、紙やすりで表面を滑らかにし、金や銅色などを塗装します。最後に前に上げた右前足にビー玉を接着剤で付けて完成です。「無心になって作れました」「久しぶりに粘土をさわって色までつけて、その工程が楽しかった」など笑顔を浮かべ、受講生は来年1年間、家庭に飾る縁起物を大切に持ち帰っていました。


針金にアルミホイルを巻いた骨組みや角、目玉などの部品は事前に用意。まずは、骨組みに粘土を張り付けて、形を作っていきます。 井上さんは「最初は細目にして、後で肉付けを」「足は鳥のように三本爪に」など細かくアドバイス。受講生は井上さんが手がけた完成品を手本に、粘土を扱っていきます。「動きがあって、強そうに見えるわ」「私、センスないわ」など軽口を交わしながら、納得できるまで形を整えていきます。


この後、角やひげを差し込んだり、鼻の造形をしたりと顔全体を仕上げていきます。次に背びれ作りです。背中の部分をつまみ道具で切り込みを入れます。受講生は手を水に濡らし、粘土を伸ばして質感を出すなど工夫を凝らしていました。


じっくり乾燥させた後、紙やすりで表面を滑らかにし、金や銅色などを塗装します。最後に前に上げた右前足にビー玉を接着剤で付けて完成です。「無心になって作れました」「久しぶりに粘土をさわって色までつけて、その工程が楽しかった」など笑顔を浮かべ、受講生は来年1年間、家庭に飾る縁起物を大切に持ち帰っていました。




2023年11月10日
チームオーバーレブ プラモ展 & プラモWS のご報告!
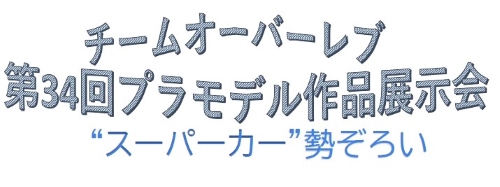


今回のテーマは「スーパーカー」。会員が展示会に向けて仕上げたフェラーリやランボルギーニ、ロータス・ヨーロッパ、ホンダNSXなど名車の模型がずらり。ムラなく丁寧に塗装し、エンジンの部品なども細かく作り込まれ、エンジンルームのドアが開閉出来るものも。中には地元スーパーの商用車や街角の風景に車を溶け込ませたジオラマも展示されました。また、凝った作りの戦車や帆船、戦闘機なども愛好家の目を奪っていました。




テレビ番組でも活躍し、「情景王」の異名を持つプロモデラーの山田卓司さんを招いての交流会があり、模型作りの上達には「優れた作品を見て参考にする」「対象物に実際に触れて良く観察する」などのアドバイスを送っていました。

 また、チームオーバーレブの会員を講師にした「はじめてのプラモデル制作体験教室」も両日にありました。小学生向けの講座で、2日間で10人が挑戦しました。
また、チームオーバーレブの会員を講師にした「はじめてのプラモデル制作体験教室」も両日にありました。小学生向けの講座で、2日間で10人が挑戦しました。

作ったのは32分の1サイズの日産フェアレディZです。説明書を見ながら、部品がそろっているかチェックした後、袋から取り出し、ニッパーで部品を切り離していきます。「ニッパーで指を切らないように」とのアドバイスに従い、慎重に取り組みます。その後、ピンセットで外したシールを部品に丁寧に張り付けたり、部品同士をはめ込んだり。接着剤が不要なタイプですが、はめ込む際の力加減が難しく、悪戦苦闘する様子が見られました。




「次はバックミラー付けようか」「シールは綿棒で押さえて」などの指導を受け、真剣に作業に打ち込み、次々と完成させました。終了後、全員が「楽しかった」と声をそろえ、次回も参加したいと答えました。保護者も「作ったことがなかったので教えてもらってよかった」「丁寧な指導ありがとうございます」と喜んでいました。子どもの笑顔がはじけた教室でした。











