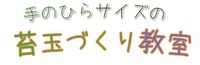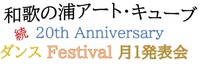2020年11月16日
クレパス画教室のご報告!
10/21㈬に開催した、アート・キューブ自主事業ワークショップ
「クレパス画教室」
なんだか毎年毎年ご報告が遅くなってしまい、本当に申し訳ございません

開催日から既に、ほぼ一ヵ月もの時間が過ぎ去りましたが…
今ここにようやく、ワークショップの模様を掲載する次第です

※教室当日、開始のご挨拶時にお伝えした通り、
参加者さんの制作中のお顔を隠すことなく、
撮影した写真をそのままブログ掲載させて頂きます。
当日は撮影にご協力くださいまして
ありがとうございました

今年の受講者は15名の方々。
昨年は先生のご厚意により、20名まで増えた人数での開催が
かないました。
しかしコロナ禍の今年は、募集定員通りの
(C1制作室の現在の定員いっぱいの)
15名ちょうどで、
ワークショップ当日を迎えることに。
キャンセル待ちの方がたくさんいらしたのですが、
全員に参加して頂けず残念でした

講師は昨年に続き、
Doi絵画教室の
土井久幸先生

参加者さんの中には、遠く白浜のご自宅から電車でアート・キューブまできてくださった方も。
それほどに講師の土井先生は大人気なのですね

画家としての才能だけでなく、きっと優しいお人柄も人気の理由です

(ちなみに、昨年のワークショップの様子はこちらです)
↓
今回のクレパス画制作のテーマは、
「光と影を美しく描く」

今年も、先生が用意してくれた風景写真が題材です。
昨年はストラスブールの風景がテーマでしたが、
今回のものもフランス郊外の写真かと思います。
陰影に富んだ、雰囲気のある風景写真。
なるほど…
これは今回のテーマに相応しい題材ですね

よい絵が描ける予感たっぷり

その風景写真にトレース紙を重ね、構図を写し取り、
そこにクレパスで着色していく…という形のワークショップ。
風景のスケッチから全部描くとなると時間がかかり大変ですが、
この「写真を利用する形式のワークショップ」なら、
クレパス画が初めての方でも安心して
参加して頂けるわけです

それでは以下に、今回のワークショップの写真を掲載致します

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
先生の用意してくれた題材写真は2種類。
どちらも同じ写真なのですが、
1つはカラーの写真、
もう1つは、キャンバスと同じサイズのモノクロ写真。
制作の第一段階として、まずはモノクロ写真に
薄いトレース紙を重ね、鉛筆で構図を描き写していきます。


これは、先生が描き写した構図。
手慣れていらっしゃるので、一瞬で描けてしまうのですね


トレース紙の裏側を鉛筆で塗りつぶし、
その面がキャンバスに接するように重ねます。
そして構図を再度なぞって描き、キャンバスに
転写させるのです。

この転写時は、大まかなラインを描くだけでOK。
およその位置がわかればよいです。
この後、直接キャンバスに描き込んでいきますので。

デッサンを描き込んでいく画材は鉛筆、
あるいは木炭のペン。
先生のオススメは木炭です。
しっかり描ける上に簡単に消せる、という
便利な画材であるとのこと。

まずは木炭でしっかり濃く描き込み、後から指で
ぼかしたり、練りゴムや布でふき取って消したりします。
絵の陰影や奥行き感は、この着色前の木炭デッサンの
段階でも表現していくそうです。
目を細めた状態で見ると、陰影と明るいところを
見極めることができます。

みなさん、すごくお上手ですね

木炭デッサンが完成したら、布でデッサン全体をはたきます

あまりにデッサンの黒が強すぎると、クレパスの着色時に
さすがに黒が目立ち過ぎるため、布ではたいて
デッサンを全体に弱める…とのこと。

先生のデッサンも完成したようです。
その後、スプレーを吹き付け、デッサンを
キャンバスに定着させました。
さて、いよいよクレパスによる
着色を始めます


ちなみにこれは、先生ご愛用のクレパスのセット。
ここから先生の手によって、素晴らしい絵画が描き出されるのですね


先生の用意してくれたカラーの写真を見ながら着色していきます。
まずは、大まかなを部分を単色で下塗り。
光の当たる部分など、明るいところから塗っていくそうです。

その後ペトロールという揮発油を、ハケで叩くように全体に塗ります。
これで、画面が少しぼやけた状態に。
そのぼやけた画面を背景として、その上にポイントとなる
細部を描き込んでいき、立体的な作品に仕上げていきます。
樹木、橋の欄干、建物、車、人物などを着色し、形や質感を整えていきます。

そして、みなさん青色をたくさん使っておられるように見えます。
そういえば、土井先生の作品集を拝見すると、
青を基調とした色調のものが多いような…

丁寧なアドバイスをしてくださる土井先生。

下の写真は、「僕はこんな感じで、後からここに白を入れたりするんです」と、
先生自身が使われる具体的な技法を伝授なさっている場面。

着色したクレパスに、指や布、ヘラなどを使って
微細な部分表現を加えていきます。
クレパスを盛り上げて、油絵と同じような
立体感や重厚感を出すこともできます。
描き足したり、こそげ取ったり、こすってぼやかしたり…
足し算や引き算を繰り返し、何度も何度も「推敲」を
重ねることができるのが、クレパス画の魅力ですね

そして…
みなさん、作品が完成したようです


どなたも、とても素晴らしい出来上がりですよ


全く同じ題材写真を元に描いていても、それぞれに違った
雰囲気の作品となっていました。
やはりアートには、制作者の個性が表出されるものですね

最後に、クレパスワニスという定着スプレーを吹き付けます。

先生の作品も完成。

みなさんを教えて回りながら、色々なフォローのため
手が止まったりもしつつ、よく「片手間」でこんなに
描けるものだなぁ…と驚きます

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
土井先生の作品を目にすると…
それが一枚の「絵画」であるにも
関わらず、連続的な映像が
展開されているかのような感覚を
おぼえます。
描いたその瞬間だけではなく、
前後の時の流れまでもが、
クレパスの画面から次から次へと
にじみ出てくるのです。
趣ある西洋の街並みから。
年月を重ねた石畳から。
人々の日常の営みから。
…そこに息づく物語が、
見る者に様々なことを
語りかけてきます。
心を奪われ、ただただ
見入ってしまう絵画です。
私は最終的に、
風景画や人物画というものではなく、
「情景画」とでも言おうものに
行き着きたいと思うのです。
土井先生は以前、
(昭和会賞受賞記念の個展の際、
刊行された画集のご挨拶文にて)
そのように書かれていました。
そう、「情景画」と表現すれば…
それで、すべて納得がいきます。
ただ技巧に任せ、景色や人間を
表面的に描くのではない。
それらに内在する歴史や人々の
心模様など、何もかもが
余すところなく描き出された
「情景画」なのですね。
でも、その「情景のあれこれ」を
見ているのは、実は私たち自身の
心の内奥。
先生が、ご自身の作品に
寄せられるべき感想を、
具体的に方向づけなさることなど
あり得ない。
正解も間違いもなく、ただただ感性の
おもむくままに観賞してもらいたいと、
先生はお思いなのでしょう。
それでもやはり、見る者がこんなにも
心揺さぶられ、様々な情景を
想起できるのは、この作品を描いた
土井先生のお力です。
こんな作品が描けたら、どんなに
素晴らしいことでしょうね

Doi絵画教室さんのホームページに先生の作品も掲載されているので、ご関心おありの方はそちらをご覧ください

アート・キューブではまた来年度も、
土井先生の絵画教室を予定しております。
今年参加してくださったみなさんも、
今回はご参加がかなわなかった方々も

次の機会にはぜひ