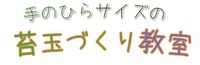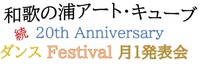2019年01月11日
HAPPY NEW YEAR past is past …
既にお正月は終わり…
松が明け、本日は鏡開き。
そんな今頃になっても、まだお正月ネタを投稿しようとする、毎夜お屠蘇(というか、ただの日本酒)を飲んでいるわたくしC職員でございます
あ、その前に、まずはイベントの告知です
1月のイベント情報にも掲載しておりますが…
1/13(日)は、
和太鼓ワークショップの発表公演 と
黒潮躍虎太鼓保存会の方々の和太鼓演奏会 です
13時開演、入場無料ですので、どうぞ観覧においでくださいませ
なお、お越しの際は、恐れ入りますが、300m南にある有料の万葉館駐車場(片男波公園駐車場)をご利用くださるよう、よろしくお願い申し上げます


さて、アート・キューブ玄関の左右には、職員たちが年末に手作りした門松が置かれていますが、受付カウンターにはこのお正月飾りが

アート・キューブの折り紙シスターズ長女(門松を鬼瓦権造のような服装で制作していたP職員)の手作りです。
さすがは器用なP職員、紅白のツバキの花を紙で見事に作り上げました。

黄色いおしべも非常に良くできています。
わたくしC職員は、こういう美しいものを作る能力に著しく欠けているため、シスターズの作品には毎回感心してしまいます
これは、自治会長さんがくださったもの。
和歌浦天満宮の干支の置物です。
黄金のアイシャドウを入れるとは、いささかカブキモノっぽい亥ではありませんか

では今回C職員は、お正月の間に食べたお雑煮の話題をば…
ユネスコ無形文化遺産に登録されている和食。
現代人の日々の食卓には、純粋な和食がのぼることが少なくなってきています。
それでもお正月ともなれば、お雑煮や御節を用意する家庭は多いかと思います。
C職員は子供の頃、元日の朝、根菜類の煮える香りと白みその芳香を嗅ぐと、大いに心ときめいたものです。
その気持ちは、●十年経った今も変わらず…
アート・キューブには調理室がないので、残念ながらこういう食に関する文化活動では、お部屋をご利用頂けないのです
でも、ちょっとC職員の垣間見たお雑煮の世界をば、ここにご紹介させて頂きます。
これは、2019年1月1日の、C家の雑煮。

小さな椀に無理やり多くの具材を詰め込んだため、いささか暑苦しい風情。
椀の中の構成は、ほぼ和歌山の代表的なお雑煮かと思います。
汁は白みそ、出汁は…私は無精をして市販のだしの素を使ったけど、関西では主にコンブやカツオなのでしょうか。
餅は丸餅。
私の実家では、餅は焼かずに入れ、汁の中で煮て柔らかくしていましたが、この写真は焼いた餅を盛り付けの段階で後入れしています。
青味大根、金時人参、里芋は輪切りに。
薄揚げも入っていますが、実家の母は豆腐も入れていましたね。
トッピングには真菜。
あと、うちの実家では入れていなかったのだけど、和歌山では写真のように青海苔も散らす家庭が多いようです。
これは、その翌日、奈良県十津川村の朝食のお雑煮。

やはり白みそです。
香り高い出汁の風味が、C職員作のものとは段違いに良い。
丸餅は焼いておらず柔らかいけど、とろけて他の具材にくっついたりはせず、美しい佇まい。
里芋と花形のニンジン、そしてミツバが浮かんでいる
古い温泉宿だったのですが、お雑煮だけでなく、他のお食事もとても美味しいところでした
これは数年前のお正月、和歌山県勝浦地区内の宿で頂いたもの。

白みそより、少し茶色がかっているような…自家製の味噌かもしれない。
出汁は…何だろう?もしかして鮎だったり?
このお雑煮の出汁の風味、普段口にする味噌汁とはなかなか異なる味わいで、とても美味だったのです。
餅は、大きな楕円形のような形に作ったものを輪切りにして、それを焼いて入れています。
これは、我が家みたいにオーブントースターでチンしたのではなく、網の上でちゃんと焼かれたお餅で非常に香ばしい。
花形のニンジン、細かく切った薄揚げ、そして白菜も入っていた。
やはり宿を長年切り盛りしているご高齢のご婦人は、ホントに料理上手だなと感激します
この美味なるお雑煮、間違いなく素晴らしい日本文化であり、芸術であると思います。
これは5年くらい前の元日、山口県湯田温泉で出会ったお雑煮。

お澄ましですね。
餅は、焼いていない角餅。
鶏肉と、銀杏切りの大根。
この他にも、これまでの人生でいくつかのお雑煮体験をしたことのあるC職員ですが、画像と記憶に残っているのはこのくらい…
どこかで、小豆あん入りのお餅のお雑煮を食べたことがあったかもしれないけど、どこの地域だったかな…?
そうそう、先日NHKのテレビ番組で観たところによると、白みそ雑煮は関西圏と四国の一部、赤みそは福井県と三重県の一部、小豆雑煮は中国地方の日本海側あたり、その他の大部分の地域はお澄まし雑煮…とのことでした。
でも、東海地方は赤みそ文化かな?とC職員は思ったのだけど、お雑煮に関してはお澄ましなのでしょうか?
異文化雑煮の人同士が結婚すると、お雑煮の味つけでなかなか揉めたりしそうですね
可能ならば、そもそもの「お雑煮」というものの始まりについてなど、深く掘り下げて書いてみたいもんですが、C職員はそんなに勉強熱心な人物ではないため、まあこのくらいにしておきます。
(NHKの番組では確か、胃腸など疲れた臓器を労り身体を養生するために食べる汁物を「保臓」と呼び、それが「烹雑」に変化し、さらに「雑煮」に遷移していった…と解説していたかと)
現代、交通手段や情報通信手段の発達によって、人々が遠い地域を旅したり様々な情報を入手することが容易となり、お雑煮の異文化交流ができるようになったのは嬉しいことです。
しかし、お雑煮グローバリゼーションの波に飲み込まれ、日本中のお雑煮が交雑し、地域個体群のお雑煮遺伝子が攪乱されてしまったりしないかしら…と、ひとり勝手に心配になるC職員。
日本のお雑煮生態系の多様性がいつまでも保たれるよう、願うばかりです。
お雑煮の交雑というより、「お雑煮そのものが日本人に食べられなくなってしまう」というのが、リアルな日本の行く末かもしれません。
C職員はとりあえず、自分が死ぬまで和歌山のお雑煮を自宅で守り続けることにしますが、あと10年くらいしたら、餅はノドに詰めぬよう細かく切って入れたほうが良いかしら…
そうだ、C職員は年末から緩衝材で七福神を作ろうとしていましたが、布袋さんを作り、恵比須さんを作りかけたところで、えべっさんも今日で終わりとなってしまいました

これは、布袋尊(のつもり)。

こっちは、のっぺらぼうですが、恵比須天の制作途中の姿…
鯛と釣竿を作ってくっつける予定でしたが、もう時間切れで撃沈です
松が明け、本日は鏡開き。
そんな今頃になっても、まだお正月ネタを投稿しようとする、毎夜お屠蘇(というか、ただの日本酒)を飲んでいるわたくしC職員でございます

あ、その前に、まずはイベントの告知です

1月のイベント情報にも掲載しておりますが…
1/13(日)は、
和太鼓ワークショップの発表公演 と
黒潮躍虎太鼓保存会の方々の和太鼓演奏会 です

13時開演、入場無料ですので、どうぞ観覧においでくださいませ

なお、お越しの際は、恐れ入りますが、300m南にある有料の万葉館駐車場(片男波公園駐車場)をご利用くださるよう、よろしくお願い申し上げます



さて、アート・キューブ玄関の左右には、職員たちが年末に手作りした門松が置かれていますが、受付カウンターにはこのお正月飾りが


アート・キューブの折り紙シスターズ長女(門松を鬼瓦権造のような服装で制作していたP職員)の手作りです。
さすがは器用なP職員、紅白のツバキの花を紙で見事に作り上げました。

黄色いおしべも非常に良くできています。
わたくしC職員は、こういう美しいものを作る能力に著しく欠けているため、シスターズの作品には毎回感心してしまいます

これは、自治会長さんがくださったもの。
和歌浦天満宮の干支の置物です。
黄金のアイシャドウを入れるとは、いささかカブキモノっぽい亥ではありませんか


では今回C職員は、お正月の間に食べたお雑煮の話題をば…
ユネスコ無形文化遺産に登録されている和食。
現代人の日々の食卓には、純粋な和食がのぼることが少なくなってきています。
それでもお正月ともなれば、お雑煮や御節を用意する家庭は多いかと思います。
C職員は子供の頃、元日の朝、根菜類の煮える香りと白みその芳香を嗅ぐと、大いに心ときめいたものです。
その気持ちは、●十年経った今も変わらず…
アート・キューブには調理室がないので、残念ながらこういう食に関する文化活動では、お部屋をご利用頂けないのです

でも、ちょっとC職員の垣間見たお雑煮の世界をば、ここにご紹介させて頂きます。
これは、2019年1月1日の、C家の雑煮。

小さな椀に無理やり多くの具材を詰め込んだため、いささか暑苦しい風情。
椀の中の構成は、ほぼ和歌山の代表的なお雑煮かと思います。
汁は白みそ、出汁は…私は無精をして市販のだしの素を使ったけど、関西では主にコンブやカツオなのでしょうか。
餅は丸餅。
私の実家では、餅は焼かずに入れ、汁の中で煮て柔らかくしていましたが、この写真は焼いた餅を盛り付けの段階で後入れしています。
青味大根、金時人参、里芋は輪切りに。
薄揚げも入っていますが、実家の母は豆腐も入れていましたね。
トッピングには真菜。
あと、うちの実家では入れていなかったのだけど、和歌山では写真のように青海苔も散らす家庭が多いようです。
これは、その翌日、奈良県十津川村の朝食のお雑煮。

やはり白みそです。
香り高い出汁の風味が、C職員作のものとは段違いに良い。
丸餅は焼いておらず柔らかいけど、とろけて他の具材にくっついたりはせず、美しい佇まい。
里芋と花形のニンジン、そしてミツバが浮かんでいる

古い温泉宿だったのですが、お雑煮だけでなく、他のお食事もとても美味しいところでした

これは数年前のお正月、和歌山県勝浦地区内の宿で頂いたもの。

白みそより、少し茶色がかっているような…自家製の味噌かもしれない。
出汁は…何だろう?もしかして鮎だったり?
このお雑煮の出汁の風味、普段口にする味噌汁とはなかなか異なる味わいで、とても美味だったのです。
餅は、大きな楕円形のような形に作ったものを輪切りにして、それを焼いて入れています。
これは、我が家みたいにオーブントースターでチンしたのではなく、網の上でちゃんと焼かれたお餅で非常に香ばしい。
花形のニンジン、細かく切った薄揚げ、そして白菜も入っていた。
やはり宿を長年切り盛りしているご高齢のご婦人は、ホントに料理上手だなと感激します

この美味なるお雑煮、間違いなく素晴らしい日本文化であり、芸術であると思います。
これは5年くらい前の元日、山口県湯田温泉で出会ったお雑煮。

お澄ましですね。
餅は、焼いていない角餅。
鶏肉と、銀杏切りの大根。
この他にも、これまでの人生でいくつかのお雑煮体験をしたことのあるC職員ですが、画像と記憶に残っているのはこのくらい…
どこかで、小豆あん入りのお餅のお雑煮を食べたことがあったかもしれないけど、どこの地域だったかな…?
そうそう、先日NHKのテレビ番組で観たところによると、白みそ雑煮は関西圏と四国の一部、赤みそは福井県と三重県の一部、小豆雑煮は中国地方の日本海側あたり、その他の大部分の地域はお澄まし雑煮…とのことでした。
でも、東海地方は赤みそ文化かな?とC職員は思ったのだけど、お雑煮に関してはお澄ましなのでしょうか?
異文化雑煮の人同士が結婚すると、お雑煮の味つけでなかなか揉めたりしそうですね

可能ならば、そもそもの「お雑煮」というものの始まりについてなど、深く掘り下げて書いてみたいもんですが、C職員はそんなに勉強熱心な人物ではないため、まあこのくらいにしておきます。
(NHKの番組では確か、胃腸など疲れた臓器を労り身体を養生するために食べる汁物を「保臓」と呼び、それが「烹雑」に変化し、さらに「雑煮」に遷移していった…と解説していたかと)
現代、交通手段や情報通信手段の発達によって、人々が遠い地域を旅したり様々な情報を入手することが容易となり、お雑煮の異文化交流ができるようになったのは嬉しいことです。
しかし、お雑煮グローバリゼーションの波に飲み込まれ、日本中のお雑煮が交雑し、地域個体群のお雑煮遺伝子が攪乱されてしまったりしないかしら…と、ひとり勝手に心配になるC職員。
日本のお雑煮生態系の多様性がいつまでも保たれるよう、願うばかりです。
お雑煮の交雑というより、「お雑煮そのものが日本人に食べられなくなってしまう」というのが、リアルな日本の行く末かもしれません。
C職員はとりあえず、自分が死ぬまで和歌山のお雑煮を自宅で守り続けることにしますが、あと10年くらいしたら、餅はノドに詰めぬよう細かく切って入れたほうが良いかしら…
そうだ、C職員は年末から緩衝材で七福神を作ろうとしていましたが、布袋さんを作り、恵比須さんを作りかけたところで、えべっさんも今日で終わりとなってしまいました


これは、布袋尊(のつもり)。

こっちは、のっぺらぼうですが、恵比須天の制作途中の姿…
鯛と釣竿を作ってくっつける予定でしたが、もう時間切れで撃沈です

Posted by 和歌の浦アート・キューブ at 20:04│Comments(0)
│★自主事業イベント│★エントランスの飾り付け│門松・注連縄・正月飾り│スタッフの創作活動│★スタッフのつぶやき